2011年10月25日
ニライカナイはパラオ人

二ライカナイとは沖縄に伝わる、海の向こうの浄土の意味で、
かなたの根の国が語源とする説がある。
柳田國男の海南小記にはこのことが触れられており、
八重山の南波照間(パイパティローマ)伝説とも呼応する。
しかし根の国は、日本人が死んで地下に行く所で、南方から
あるいは日出づる国からやって来る宗教観とは違う。

一方で、儀来河内という字をあてている例もある。
南城市の受水走水(ウキンジュハインジュ)の案内板には、
琉球国由来記の引用でギライカナイと記されている。

大震災の被災地を調査して歩くうちに、その土地の地名の持つ言霊に、
驚かされたことがある。
言葉にその土地や人の歴史、想いが込められていたのである。
二ライカナイとは、発音が同じNgirai Kanaiというパラオ人の
名前であると推測される。
パラオ語はンから始まる音が多く、非常に聞き取りにくい。
接頭語がNgで始まるので、二ライともギライとも聞こえる。
私のパラオ人の同僚はNgiraibai(二ライバイ)と言い、
Ngiraiを冠する名前は他にも多い。
ファミリーネームのKanai(カナイ)も一般的で、アイライ州の州知事や
上院議員のカナイさんが有名である。
パラオは日系の名前が多いが、戦前からあった名前だという。
ちなみに彼の息子の名はニラロイ・カナイという。
パラオは3000年前に、南中国から文明が伝わり、ミクロネシアでは最も
古い歴史のある国で、縄文時代に、既にパラオ土器が産出されていた。
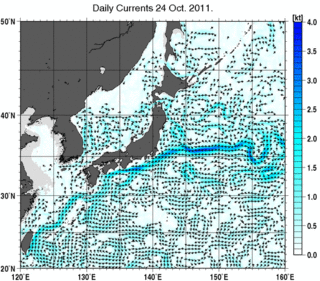
太平洋の海流の流れを見ると、黒潮はフィリピン、台湾方面から
沖縄の西海岸を北上し、伊良湖岬に達する。
柳田國男の拾った椰子は、フィリピンからであった可能性が高い。
沖縄の東海岸と久高島にたどり着くには、沖縄本島を北から1周するか、
南からの黒潮の一支流に乗るしかない。
その先は2000km離れたパラオしかない。
一方、八重山近海には黒潮反流という南向きの海流がある。
パイパティローマを信じた波照間島の住民の向かった先は、
台湾ヤミ族の住む蘭嶼島と言われているが、黒潮を横断しなければならない。
それ以外の南の島はやはりパラオだけである。
沖縄の久高島に漂着したパラオ人のNgirai Kanaiが
持ち込んだ道具や技術が、古代沖縄に影響を与えたとしても、
おかしくはない。
今までのニライカナイやパイパティローマ論争に、
パラオの名が出てこなかったのが不思議である。
Posted by Katzu at 14:04│Comments(0)
│沖縄
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。














