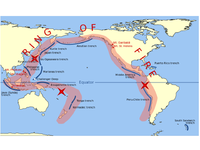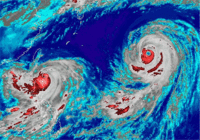2012年01月30日
統計学の罠
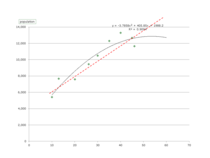
先日、知人から検定や標準偏差の相談をうけ統計に関する話をしていた。
統計学の類は、アンケート分析や構造データの棄却などで使うが、
基本的な説明ができず、無知と統計学の難しさを感じた。
都市マスタープランの将来人口予測を行う場合は、幾つかの予測式を
あてはめたものと、実質的な積み上げた人口を比較して、
目標人口を設定するが、予測通り進んだ例は、知る限り少ない。
その理由の一つは、ハードな計画上の思惑が存在するからである。
純粋にプロが、意図してもしなくても、統計の陥りやすい間違いは
1、確率の分母に当たる母集団対象の解釈が違う。
2、確率の分子に当たる対象となる事象の解釈が違う。
3、数値上の有利な式を選択してしまう。
環境影響予測、経済指標予測など理屈を積み上げる生業は、
時に数字の罠にはまってしまう例はいくつもある。
統計学上は、データの時間的、地理的、自然条件的な均一性が
証明できなければ、正確な結果は得えられない。
その条件を知らない人に対しては、数値だけが独り歩きする危険性がある。
東京大学地震研究所は23日、首都圏でマグニチュード7以上の
直下型地震が、4年以内に起こる確率は70%という数字を発表した。
首都圏に住む人、仕事をする人にとっては驚愕の数字である。
首都圏への不動産投資はハイリスクに、人の移動に制約が出るかもしれない。
この予測は、地震の回数と頻度がべき乗になるという
『グーテンベルグ・リヒターの法則』に基づいて予測されたものである。
今回の東北地方太平洋沖地震の余震データが、
この法則に合うことから導き出されたものである。

一方、この理論に疑問を抱く人もいる。
これはカリフォルニア地震以降の地震学の成果であるが、
過去の大地震に対しては、このような詳細データは皆無であり、
それぞれの条件は異なる。
これを先の地震の余震と見るか、新たな活動と見るか
見極めは難しいと専門家は見ている。
それとも、一般の人は、今までの地震予測の結果から、
これを鵜呑みにする人は少ないのだろうか。
今大切なのは、その兆候を捉え観測し、研究するとともに、
同時に防災計画を遂行することである。
震災前から座礁クジラが増えてる原因、富士5湖でワカサギが
釣れなくなった原因とか調べていくと、地底の環境の変化が、
リアルタイムに解る可能性がある。

むしろ、現在JAMSTECが行っているような、海溝付近の深々度海底調査、
実質的な津波観測システム網の構築、地球シュミレ-タなどに
予算と人的配置を向けるべきではないのだろうか。
もちろん、地震に対する防災意識と準備は常に必要である。
一方、政府の地震調査研究推進本部は、30年以内に地震を起こす
可能性のある(各0~18%)活断層32か所を発表した。
全国地震動予測地図は30年に一度、震度6以上の地震に
見舞われる確立の高い地域を表したたもので随時更新している。

これは各保険や、評価指標にまだ使われているが、
活断層が原因なのか、大陸プレート移動なのか原因と対象が違うため、
前段の予測を含めると、トータル的に何が正しいのか、素人にはわからない。
マスコミにも問題があり、数字だけでなく、
その根拠になった考えや背景も報道する義務があり、
研究者も素人にわかりやすい説明を心がけるべきであろう。
Posted by Katzu at 12:24│Comments(0)
│大震災
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。