2013年05月15日
ものづくり日本とデザイン力

海外に行くと、中国製や韓国製の製品が街にあふれ、日本製で目立つのは、
家電の古い看板と中古のトヨタとDATSUN位だ。と感じたのは5年ほど前からで、
ものを作って輸出する日本はどこに行ったのだろう、と危惧したものである。

技術力にしても、後発国はグローバル化が進み、日本の技術者のマニュアル化した業務と、
専門的な仕事に偏る二面的な閉塞性が、グローバル化を遅らせその差は縮まった。
今さら、日本の技術力は世界一といばっても仕方ない。
いずれ真似され、安く大量生産販売されれば同じ繰り返しになる、と悲観的になる。
日本人として優れた所を見せようとしてあがいても、それは単なるアイデアだけで、
郷に入った条件のものは提供できない。
日本人のものづくりで、優れた所は何なのだろうと悩んでいたが、結局そんなものはなく、
同じ立場で早くグローバルスタンダードに立つことが必要だと自戒するに至った。

しかし、発展途上国に贈与された公共物や、アジア系資本の建物を見て感じたことが多々ある。
ものの経済性や機能性は変わらなくても、そのデザインが設置された街に合わない例である。
日本人が工業後進国に比べ優れているのは、もののデザイン力である。
かつては、ものまね日本と欧米から揶揄され、安く大量の製品が世界を凌駕し、技術力も発展した
経験から、今では製品を真似される逆の立場に変わった。

世界の富が集まるアジアの大都市は、さすがに個性的で目を見張る巨大な建造物が多い。
しかし、街に目をやると、標識から街灯に至るまで、周囲の景観に配慮した生活レベルではない。
日本の公共物はスマートにマニュアル化され、整然としすぎ面白みに欠けるという欠点があるが、
少なくとも計画・設計者は環境デザインというものを意識する。

中国は貧富の格差があり、中華思想がデザインを自己主張に偏らせている面がある。
日本でも最近になって、景観に配慮して電柱地中化を進めるようになったわけであるが、
近代化を先行させた経験が、総合的なデザイン力の違いを生んでいると感じる。

現在は、カーデザインから装飾デザインにいたるまで世界的に認められた設計デザインは多い。
その中で注目されるのは、日本伝統の折り紙技術を応用した1枚の型紙デザインである。
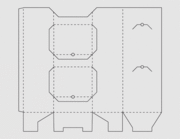
試しに、扁平の3段ボックスをCADで設計し、平面的に書いてみるが、意外に難しい。
3次元CADなるものもあるが、折りの角度、段ボールの厚味や、紙一枚の連続性やら
空間把握ができないと、こんな単純なものでも設計はできない。
自分の手で書いて紙を折って作って遊ぶうちに、ようやくイメージすることができた。
恐らくプロの型紙デザイナーも、同じことをして新しい物を創造するのだろう。
段ボールを折り立てていく過程で細かい問題も出てくるが、
その時は空間把握にフィードバックし解決されていく。

小さな装飾デザインから街のデザインに至るまで、ブレーンストーミングを繰り返しながら、
同じような過程をたどる。その表現手段として3DcadやCGが使われる。
そこからものづくりは始まり、それは経験を積むことで簡略化し、製品製作を繰り返すことができる。
日本人はようやく、周辺の環境にあわせたデザインを提供できるようになったのかもしれない。
さらに、そのパーツを含めた全体の環境をデザインしていくということは、さらに複雑で深く正解がない。

Posted by Katzu at 19:33│Comments(0)
│環境デザイン
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。















