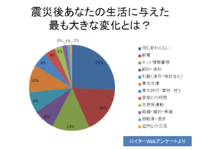2015年12月01日
ミニマリストとカーシェアリング
COP21がパリで開幕したが、今年で気候変動の公約はまとまるだろうか。
アメリカではオバマ大統領のグリーンニューディール政策は6年が経ち消え、
自国の公害でやっと目が覚めた中国は、2050年までに60~65%の
CO2削減目標を初めて掲げた。ただ、このGDP当たりというのがくせ者で
所得倍増を謳う中国の政策通り進めば、削減量は実質0%に近づく。
COPで本来語られるべき地球環境問題が、南北問題、経済交渉、
政策PRにすり替わっているのが残念である。

2081~2100年気温上昇:IPCC
この一つの地球を、一つの大陸、一つの島、一つの街と狭めていくと、
最終的に、一つの部屋という一人の小さな環境にたどりつく。
週末に海山川と遊び、音楽を聴き奏で記録し、自前食を作っていくうちに、
知らぬ間に家中が使わない物であふれかえっていた。
捨てる勇気もなく、整理も面倒で新しい物への執着も薄らいだ。

サラリーマン生活を止め、物を持たないゼロの生活をスタートすると、
世の中には何と無駄なものが多いのかということに気が付いた。
電化製品はパソコン、テレビ、冷蔵庫だけで生活すると、
電気光熱費は月3000円程度の省エネ生活で済む。 ただし、
こだわりが多くある分、総支出はあまり変わらないという矛盾が生まれる。
若い世代を中心に、合理的な『断・捨・離』により、モノを持たない
シンプルライフを標榜する人を、『ミニマリスト』と呼んでいるらしい。
100円生活の芸能ネタや貧乏差別としてとらえる人もいるだろう。
しかし、いずれ社会に還元し、健康な生活を目標とすれば、
単なる消費社会へのアンチテーゼだけではなく、若者だけでなく
これからの少子高齢化社会の1つのスタイルになるのかもしれない。

車を捨てる勇気というのも必要で、全国の自動車移動距離を登録台数で
換算すると、年間走行距離は平均3600kmというデータがある。
いかに動かさない自動車が多いかということで、週末だけ使う人も多い。
今年、日常生活での自転車の走行距離は3000kmを超えたが、
ロードバイクのサイクリストとしては決して多い数字ではない。
このまま行けば車の走行距離でCO2を換算すると、年間500kgとなり
一人当たりの平均排出量2300kgの20%の削減量となる。

決まった移動はなるべく公共交通機関を使い、自由度のある遠出は
長期・短期・用途に合わせ、複数会社のレンタカーを選択利用している。
車を複数で使用する広義の意味合いとは少し違うが、今年話題となった
カーシェアリングというカービジネスシステムがある。
会員になれば、手軽に短時間でも使えるセルフレンタカーサービスである。
バス・タクシーとの競合になり、自家用車の抑制につながると言われ、
生活改善というより経済的な理由で、都会を中心に注目されているが、
まだ地方部では安いレンタカーとの違いが浸透されていない。

気候変動対策は人の消費生活の質の変化だけでは不十分で、
国の形態や国策の違いが大きく影響する。
北朝鮮は周囲と比べ国境線がわかるほど夜は暗く不気味だが、
都市の消費エネルギーは少ないうえに、原発開発を進めているため、
皮肉にも気候変動に負担をかけない優等生ということになる。
最も無駄なエネルギーを大量消費する戦争こそ、なくすべき地球の環境問題だろう。

アメリカではオバマ大統領のグリーンニューディール政策は6年が経ち消え、
自国の公害でやっと目が覚めた中国は、2050年までに60~65%の
CO2削減目標を初めて掲げた。ただ、このGDP当たりというのがくせ者で
所得倍増を謳う中国の政策通り進めば、削減量は実質0%に近づく。
COPで本来語られるべき地球環境問題が、南北問題、経済交渉、
政策PRにすり替わっているのが残念である。

2081~2100年気温上昇:IPCC
この一つの地球を、一つの大陸、一つの島、一つの街と狭めていくと、
最終的に、一つの部屋という一人の小さな環境にたどりつく。
週末に海山川と遊び、音楽を聴き奏で記録し、自前食を作っていくうちに、
知らぬ間に家中が使わない物であふれかえっていた。
捨てる勇気もなく、整理も面倒で新しい物への執着も薄らいだ。

サラリーマン生活を止め、物を持たないゼロの生活をスタートすると、
世の中には何と無駄なものが多いのかということに気が付いた。
電化製品はパソコン、テレビ、冷蔵庫だけで生活すると、
電気光熱費は月3000円程度の省エネ生活で済む。 ただし、
こだわりが多くある分、総支出はあまり変わらないという矛盾が生まれる。
若い世代を中心に、合理的な『断・捨・離』により、モノを持たない
シンプルライフを標榜する人を、『ミニマリスト』と呼んでいるらしい。
100円生活の芸能ネタや貧乏差別としてとらえる人もいるだろう。
しかし、いずれ社会に還元し、健康な生活を目標とすれば、
単なる消費社会へのアンチテーゼだけではなく、若者だけでなく
これからの少子高齢化社会の1つのスタイルになるのかもしれない。

車を捨てる勇気というのも必要で、全国の自動車移動距離を登録台数で
換算すると、年間走行距離は平均3600kmというデータがある。
いかに動かさない自動車が多いかということで、週末だけ使う人も多い。
今年、日常生活での自転車の走行距離は3000kmを超えたが、
ロードバイクのサイクリストとしては決して多い数字ではない。
このまま行けば車の走行距離でCO2を換算すると、年間500kgとなり
一人当たりの平均排出量2300kgの20%の削減量となる。

決まった移動はなるべく公共交通機関を使い、自由度のある遠出は
長期・短期・用途に合わせ、複数会社のレンタカーを選択利用している。
車を複数で使用する広義の意味合いとは少し違うが、今年話題となった
カーシェアリングというカービジネスシステムがある。
会員になれば、手軽に短時間でも使えるセルフレンタカーサービスである。
バス・タクシーとの競合になり、自家用車の抑制につながると言われ、
生活改善というより経済的な理由で、都会を中心に注目されているが、
まだ地方部では安いレンタカーとの違いが浸透されていない。

気候変動対策は人の消費生活の質の変化だけでは不十分で、
国の形態や国策の違いが大きく影響する。
北朝鮮は周囲と比べ国境線がわかるほど夜は暗く不気味だが、
都市の消費エネルギーは少ないうえに、原発開発を進めているため、
皮肉にも気候変動に負担をかけない優等生ということになる。
最も無駄なエネルギーを大量消費する戦争こそ、なくすべき地球の環境問題だろう。

Posted by Katzu at 19:34│Comments(0)
│エコ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。