2013年03月16日
旅の伏線-インパールの戦い

この時期、首都ヤンゴンから北に向かうと、旅人は困難な状況に出会う。
土地は乾き、川は枯れ、大地は熱を放出し、生を求める動物たちは静かに時が過ぎるのを待つ。
旅人にとっては、止まっても、動く車で休んでいても、身体のエネルギーは放出されていく。
正確な地図はGoogleMapしかなく、時間をかけ計画を練る余裕もなく、
今回はガイドブックに頼ってしまった。
世界で一番暑くなるこの雨季の前に、計画的な野外活動すること自体、
この地域では無謀な行為である。
それを継続すれば、体力は消耗していく。
資金の調達と余裕ができればいいが、このミャンマーの発展と
インフラ整備の状況と換金システムを知らず、ずさんな計画があだとなった。
登山では、エスケープルートとエスケーププランを必ず検討するが、
このビルマの地方ルートはほとんど1本だけで変更ができない。

バガンの初日の夜、腹痛、下痢、震え、悪寒、吐気が起きた。
日本の薬は全然効かなかった。
衛生環境の整わない地域での滞在では、1度は下痢にかかるが、
今回のこの重篤な症状は初めてである。
何かにとり憑かれたようでもあった。
マラリヤ、コレラ、デング熱を疑った。
宿で紹介してもらったクリニックに行った。
向いにある喫茶店のような医院だった。
先に待っていた10人ほどのローカルの患者は番号札をくれたり、色々世話を焼いてくれた。
中国系のドクターは、慣れているようで、尻に注射をし、5種類の薬をくれ5分で終わった。
今回は嫌な予感がして、旅行保険に入って入院しても安心だったが、たった10ドルだった。

便の検査は?熱は?感染症は?と心配してしまうが、これでOKだという。
次の日、信じられないように回復したが、2日間、水とスープだけだった。
熱く弱り切った身体に、中華系食堂で山盛焼きそばと生野菜、
地ビール2本を飲んだのがいけなかったようだ。
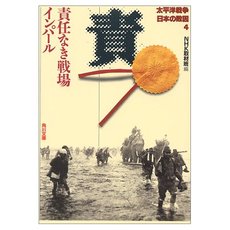
この旅が69年前のインパール作戦と同じ日程、経路、経過をたどっていることに
気付いたのは、文庫本を読みながら、バンコクを出た頃だった。

旧日本陸軍の牟田口司令官と幕僚達は、自分と同じ計画の誤りを犯していたのである。
それは雨季に入る前に、ビルマ平原を北上し、5月前にインパールを攻略するために、
支援も交代もない、前進だけの計画性のない無謀な戦いを急いでいた。
前年に泰緬鉄道を完成させ、シンガポール・タイ方面からラングーンへ兵を増強、
ビルマ中北部マンダレー近くを拠点とした。
3月8日、インパール、コヒマへの進軍が始まった。
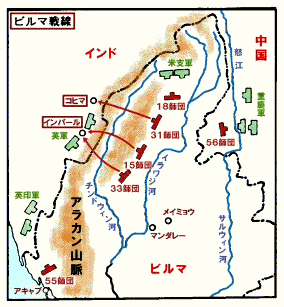
ここから一人40kgのリュックを背負い、1日30kmもの行軍、途中の山脈は3,000m級で、
体力を奪われ、弱った胃腸に細菌性の胃腸炎が蔓延したという。
この時期の痩せたひとこぶ牛を見ていると、農用牛を軍事輸送の中心に
置かざるを得ない状況が、すでに建前の戦争であったとわかる。
残った最後の1頭を食べた時、兵士達は既に肉を消化できる体でなかったという。
この熱帯では、何も食べれず、喉が渇き水だけを飲み、
エネルギーが消耗していく状況では、絶望感だけが取り残される。

マンダレー周辺は、ビルマの歴代王朝が遷都した都が多いが、アユタヤ王朝を滅ぼした
コンパウン王朝の破壊王シンビューシン王も、近くのインワを拠点にしていた。
しかしその栄華を今に伝えるものはほとんどない。
マンダレーの最後の王宮跡も、日本軍とイギリス軍の市街戦により廃墟になった。

ここからインパールまでは直線で400kmに満たない。
しかし、それは机上の話である。
イラワジ川を渡り対岸の山を越えると、日本兵の死体が数mおきにあったという
白骨街道と呼ばれたチンドウィン川沿いの盆地に出る。
今の自分にはそこに行く体力も、時間も装備も資金もない。
このままこの地に留まれば、すぐに雨季が来るだろう。

イラワジ川対岸のミングォンの寺院から望む山は、郷里の山にも似て、
映画“ビルマの竪琴”のように、帰還兵が仏教に帰依したとしてもおかしくない。
現場を知る1兵卒の置かれた状況が、わかるような気がした。
この地で、7万人もの死者を出し、帰還兵は1割程度だったという凶気の戦争犯罪は、
日本人の危機管理能力の弱さと、組織の責任回避と、建前の政略が生んだ悲劇だが、
今もその日本人の基本的体質は変わらない。
同じ日本人として、何でこんな所まで戦争しに来たのだろう。
南洋のきれいなサンゴ礁の島や、東南アジアの農村風景を見ながら、
その戦跡に立つと、繰り返しその想いを強く抱いた。
そして、一陣の風が去った後、周囲の自然や風景が、時間を止めたまま凍りつくのである。

Posted by Katzu at 10:23│Comments(0)
│アジア
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。















